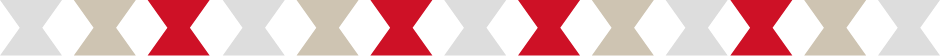2025年2月14日から18日にかけて、鈴鹿剛教授率いる四国大学の学術代表団と、日本の上板町の代表者がヨルダンを訪問しました。今回の訪問の目的は、「フレンドリー・シティ・イニシアティブ」の一環として、ゴール・アル=サフィおよびゴール・フィーファ地域における藍(Indigofera tinctoria)の復活に関する調査を行うことでした。また、2025年大阪・関西万博終了後も継続的な協力を図るため、両国間の新たな協力の可能性を探ることも目的とされました。このプロジェクトは、JICA(国際協力機構)がヨルダンに提供する国際協力の枠組みの一環として、農業プロセスの開発、生産効率の向上、知識の継承、地域社会への研修および教育の提供を目的として組み込まれる可能性があります。
訪問プログラムの一環として、ゴール・フィーファで2つのワークショップが開催されました。1つ目のワークショップでは、地元の女性たちが日本の藍染め技術を学びました。2つ目のワークショップでは、ゴール・フィーファの学校の生徒と、Zoomを通じて参加した日本の上板町にある高志(たかし)学校の生徒が共同で藍染めの実技を行いました。
また、代表団はプリンセス・タグリード開発・研修研究所を訪問し、ゴール・フィーファおよびゴール・アル=サフィの地域社会と共にこのプロジェクトを展開していくために必要な次なるステップについて議論しました。具体的には、藍の栽培や管理方法に関する研修、適切に土地を整備する方法などについて話し合われました。
さらに、代表団は副特命全権代表と共に教育省を訪問し、初等教育局のアフマド・アル=マサーフェ博士と会談しました。この会談では、両国間の教育協力の可能性について議論されました。鈴鹿教授は、STEAM(科学、技術、工学、芸術、数学)の分野における実践的な教育を学校の生徒に提供する意向を示しました。これらの技術は、藍産業において持続可能性や品質向上を図るために応用されています。
その後、代表団は観光・考古省を訪問し、リーナ・アナブ閣下と会談しました。アナブ閣下は代表団を温かく迎え、このプロジェクトを継続的に支援し、投資を行っていくことに強い関心を示されました。彼女は、駐日ヨルダン大使を務めていた際から、藍の栽培とその用途に関心を持っていたと語られました。また、彼女は藍の栽培過程、染料の抽出、製品製造の各段階についてまとめた自身の研究を代表団に紹介しました。
最後に、代表団はJICAヨルダン事務所長も同席する中で、在アンマン日本大使閣下と会談しました。この会談では、代表団がこれまでに実施した活動の概要を報告し、ゴール・アル=サフィおよびゴール・フィーファ地域における藍の栽培プロジェクトを支援・発展させるための方法を模索する必要性が強調されました。